苔(こけ)・コケ 三平商店
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』抜粋
苔(こけ)・コケは地表や岩の上にはいつくばるように成長し、広がるような植物的なもの。
狭義のコケは苔類、蘚類、ツノゴケ類の総称としてコケ植物を指すが、コケはそれに加え菌類と藻類の共生体である「地衣類」や、一部のごく小型の維管束植物や藻類などが含まれる。
語源は「木毛」にあり、元々は樹の幹などに生えている小さな植物の総称だったとする説がある。
自生している又は栽培されている苔は日本などで鑑賞の対象となるほか、イワタケなど食用の苔もある。

コケは蘚苔類(せんたいるい)という木の幹や岩の上、土手、石垣などに育つ植物です。
種で増える種子植物とは違って、胞子や匍匐で増える植物です。
根を持たず、からだ全体で水分を吸収し、光合成をします。
空中湿度が保たれた環境や安定した水量が流れる渓流などはコケの生育に適しており、種類豊富に群生します。
苔は日本庭園や盆栽で昔から利用されていましたが、最近は苔玉やテラリウム(コケリウム)、ガーデニングなどで人気が出ています。
苔の育て方のポイント
- 水やりは夕方にたくさんやる。
- 水はけをよくする。
- 風あたりの強いところは苦手なので、風避けを設ける。
- 落ち葉を取り除く。光合成ができなくなり、生育を阻害する。
苔を育てるには以上のような簡単な気遣いは必要ですが、他の動植物と比較すると誰にも楽しめることが苔の魅力です。
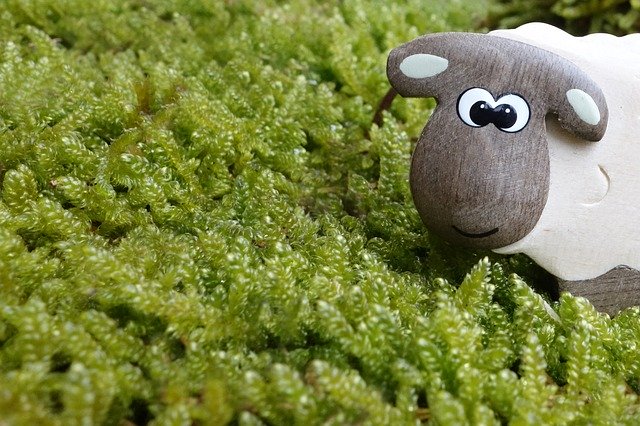
苔は夏季の蒸す時期は苦手で、逆に冬は強いので、秋に苔を蒔いて、来年の春までに、大きく育てるのがよい方法です。
強い日当たりの場所は、苔は弱ってしまうので。やはり半日蔭(木漏れ日が動く場所)で苔はよく育ちます。木陰を作ってやると良いようです。
日本国内で人気の苔

- スギゴケ
- スナゴケ
- ホソバオキナゴケ
- ハイゴケ
- カモジゴケ
- コスギゴケ
- ホソウリゴケ
- エゾスナゴケ
- タマゴケ
- クジャクゴケ
- シノブゴケ
- ウチワゴケ
- ホソバオキナゴケ
- ヒノキゴケ
- ゼニゴケ
 種類ごとに詳しく説明していきましょう。
種類ごとに詳しく説明していきましょう。
 |
スギゴケの特徴は、硬質な葉と直立する茎です。しっかりと形を作るスギゴケは、その特徴から日本庭園など景観を作る為に利用されています。
スギゴケは光合成する為、日光が必要です。ですが、熱に弱い為、直射日光を与え続けては枯れてしまいます。 |
 |
河原や山地の日当たりの良い砂質の土や岩の上、石垣などに黄緑色の群落を作る。
全日照でも耐え、性質の強い苔です。繁殖力もあるので比較的、簡単に増やすことができます。 |
 |
ホソバオキナゴケは樹木の根元、切り株、朽ち木上などに丸く盛り上がった群落を形成するコケです。
赤玉土や富士砂、桐生砂などの水はけのよい土に植え、半日陰で栽培する。 |
 |
ハイゴケは、苔玉やテラリウムでよく使われています。這うように生長する苔の一種です。
強健で生長もはやいので、育てやすくメジャーな苔です。 |
 |
カモジゴケは、日本各地に分布。
半日陰地で良く育ち、比較的湿潤地を好むが、日陰地であれば乾燥が続いても枯れることがないため育てやすい。 |


